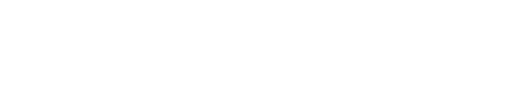「終活」は年齢を問わず誰もが考えるべきテーマですが、60代は「計画から実践へ」と移行すべき重要な転換期です。50代が将来への準備期間だとすれば、60代は実際に行動に移す実践期間。退職後の時間の使い方、健康状態の変化、そして人生経験から得た知恵を活かして、より具体的かつ現実的な終活を進めていく時期です。本記事では、60代ならではの実践的な終活アプローチについて、具体例や専門家の知見を交えながら解説します。

60代の終活計画の特徴|時間的制約を意識した優先順位づけ
60代の終活は50代とは明確に異なる特性があります。それは「時間的制約」と「身体的変化」をより意識する必要があることです。
60代の終活における特徴と50代との違い
- 時間軸の短縮:50代では10〜15年の準備期間があるのに対し、60代では計画から実行までの時間が短縮
- 健康状態の変化:50代よりも体力や健康面での変化を実感する機会が増え、より現実的な計画が必要
- 退職後の生活実態:50代は退職後の生活を想像で描くのに対し、60代は実際の退職後生活を基に終活を調整できる
- 経験による優先順位の明確化:人生経験の蓄積から、本当に大切なものが何かをより明確に判断できる時期
終活の専門家によると、60代は「選択と集中」の時期だといいます。すべてを完璧に行おうとするのではなく、残された時間と体力を考慮して、本当に重要なことに絞って取り組むことが大切だと指摘されています。
ある60代の方は「50代の頃は『いつかやればいい』と思っていたことが、60代になると『今やらねば』という切迫感に変わりました。特に親の介護や友人の病気を経験して、時間の有限性を実感しています」と語ります。
60代の終活計画と退職後の時間活用|充実感と社会的意義の両立
60代の大きな特徴は、多くの人が退職を迎え、時間の使い方が大きく変わる時期だということです。この「時間」という新たな資源をどう終活に活かすかが重要なポイントです。

退職後の時間を終活に活かす戦略
- 時間の構造化:50代までは「仕事中心」だった時間を、目的を持って再構築する
- 社会との接点の維持:退職後も社会とのつながりを意識的に保つ活動を計画する
- 新たな役割の獲得:地域活動やボランティアなど、社会的意義のある活動への参加
- スキルや経験の社会還元:これまでの経験やスキルを次世代に伝える機会を作る
高齢者の社会参加に関する研究者によれば、退職後の「役割喪失」は心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があるといいます。終活においても、「社会との接点」を維持することが重要だと指摘されています。
退職後にボランティア活動を始めた60代の方は「週に2回、子どもたちへの読み聞かせボランティアをしています。この活動が私の生活に規則性と目的をもたらし、終活を考える上でも『次の世代に何を残せるか』という視点が生まれました」と話します。
50代の終活が「将来の計画立案」に重点を置くのに対し、60代の終活は「現在の時間をどう有意義に使うか」という視点が加わります。この「今」を大切にする姿勢が、より充実した終活につながります。
60代の終活計画と健康管理|実体験に基づく医療・介護の現実的選択
60代になると、自身の健康変化を実感する機会が増えるとともに、親や同世代の友人の介護や看取りを経験する方も少なくありません。これらの実体験は、自分自身の医療や介護に関する終活計画に大きな影響を与えます。
60代における健康と医療に関する終活のポイント
- 具体的な健康課題への対応:50代の「予防」中心から、60代は具体的な健康課題への対策へシフト
- 医療・介護の現実的選択:親や友人の経験から学んだ実情を踏まえた選択肢の検討
- 在宅医療と施設選択の具体化:終末期をどこでどのように過ごしたいかの具体的な検討
- 医療に関する代理意思決定者の指定:判断能力が低下した場合に備えた医療代理人の選定

老年医学の専門家によると、60代は「フレイル(虚弱)予防の最重要期」だといいます。この時期の健康管理が健康寿命を大きく左右し、終活の選択肢の幅にも直結するとのことです。
親の介護を経験した60代の方は「母の認知症介護を通じて、自分も同じ道をたどる可能性があると実感しました。その経験から、財産管理や医療決定に関する法的準備をより具体的に進めています」と話します。
50代の「万一の場合に備えた計画」とは異なり、60代は「可能性が高い事態への具体的準備」という視点で医療・介護の終活を考える必要があります。
60代の終活計画と財産管理|「形成」から「分配と保全」へのシフト
60代の財産管理は、50代までの「形成と準備」から「保全と分配」へと明確に重点が移ります。年金生活が始まり、収入構造が変わるこの時期は、財産の管理と引継ぎについてより具体的な計画が必要です。
60代の財産管理における終活のポイント
- 収入減少を前提とした資産管理:50代の「資産形成」から60代は「資産保全」へとシフト
- 財産の棚卸しと整理の本格化:保有資産の総点検と必要な整理・統合
- 相続対策の具体化:遺言書の作成や相続税対策の実行
- 生前贈与の計画的実施:子や孫への計画的な財産移転の検討
ファイナンシャルプランナーによれば、60代は「遺す財産」と「使い切る財産」の区分けが重要な時期だといいます。50代までが「資産を増やす時期」なら、60代は「資産の配分を決める時期」とのことです。
60代の夫婦は「退職金をいくら相続資金として残し、いくら老後の生活と楽しみに使うか、具体的な数字で計画しました。50代の漠然とした計画とは違い、実際の年金額や退職金を基にした現実的な計画です」と話します。
また、デジタル社会における新たな課題として、オンラインアカウントや電子データなどの「デジタル遺品」の管理計画も60代の終活では重要性を増しています。
60代の終活計画と人間関係の再構築|本質的なつながりを深める
60代は、長年の人間関係を見つめ直し、より本質的なつながりを大切にする時期です。特に退職によって職場の人間関係が希薄化する中、残された時間をどのような人間関係の中で過ごすかを再考することも、重要な終活の一部です。
60代における人間関係の終活ポイント
- 関係の質の見直し:50代までの「量」重視から「質」重視の人間関係へ
- 家族との関係性の再構築:親役割から対等な大人同士の関係性への移行
- 地域コミュニティとの関係強化:退職後の生活基盤としての地域とのつながり構築
- 終末期を支える人間関係の構築:万一の時に支え合える関係づくり
社会心理学の研究者によれば、60代以降の人間関係は「情緒的満足度を重視する方向に変化する」といいます。若い頃の功利的な関係から、心の充足をもたらす関係へと重点が移るとのことです。
60代で地域の町内会活動に参加し始めた方は「50代までは仕事中心で地域との接点が薄かったのですが、退職を機に町内会の役員を引き受けました。いざという時に助け合える関係づくりが、自分の終活にとっても重要だと感じています」と語ります。
60代の人間関係の終活は、単に「別れの準備」ではなく、「より深いつながりの再構築」という側面が強くなります。残された時間をより質の高い関係の中で過ごすための意識的な取り組みが重要です。

60代の終活計画と住まいの選択|「今」と「これから」を見据えた現実的決断
60代は住まいに関する現実的な決断をすべき時期です。50代が「将来に向けた準備」の段階なら、60代は「実際の住環境の整備」を進める段階といえます。
60代の住まいの終活における特徴
- 身体機能の変化を考慮:50代より具体的な身体機能の変化を見据えた住環境の整備
- 地域インフラの重要性増大:医療機関や買い物環境など、生活インフラへのアクセスを重視
- 住み替えの実行期:50代での検討を基に、実際の住み替えを決断・実行する時期
- 親の家・実家の処分決断:親の介護終了後の実家の活用または処分の決断
住環境の専門家によれば、「60代前半の住まいの選択が、70代、80代の生活の質を大きく左右する」といいます。体力があるうちに住環境を整えておくことが、その後の自立した生活を支える基盤になるとのことです。
60代で郊外から都心部のマンションに引っ越した夫婦は「子どもも独立し、庭の手入れなど家の維持が徐々に負担になってきたことと、将来の通院や買い物の便利さを考慮して思い切って引っ越しました。50代では『いつか』と考えていたことを、60代で実行に移しました」と話します。
また、住まいの終活は単なる「物理的環境」だけでなく、「コミュニティとのつながり」という側面も重要です。特に60代は、住み慣れた地域でのつながりと、利便性や将来の介護のしやすさとのバランスを取ることが課題となります。
60代の実践的終活計画|すぐに始められる5つの具体的アクション
60代の終活は「考える」段階から「行動する」段階へと移行する時期です。以下の5つのアクションを参考に、計画から実践へと移行していきましょう。
【アクション1】健康基盤の強化と医療選択の明確化
- 健康診断結果に基づく具体的な対策実施
- かかりつけ医との良好な関係構築
- アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の文書化と家族との共有
- 医療に関する代理意思決定者の指定
【アクション2】財産の整理と相続準備の本格化
- 全資産の詳細なリスト作成と定期的な更新
- 遺言書の作成または見直し
- 生前贈与の計画的実施
- デジタル資産の管理と承継計画の具体化
【アクション3】住環境の最適化
- 現住居のバリアフリー化または住み替えの実行
- 将来の介護を見据えた住環境の点検と改善
- 不要な家財道具の整理・処分
- 終の棲家としての住環境の整備
【アクション4】社会的つながりの再構築
- 退職後の新たな社会的役割の獲得
- 地域コミュニティへの積極的参加
- 友人・知人との定期的な交流機会の創出
- 世代間交流の場への参加
【アクション5】ライフレビューと価値観の伝承
- 自分の人生の振り返りと記録
- 次世代に伝えたい価値観や知恵の整理
- 家族史や思い出の記録と共有
- 形に残る遺産以外の「心の遺産」の準備
終活の専門家によれば、「60代の終活の最大の敵は先送り」だといいます。「まだ大丈夫」という思い込みを捨て、具体的な行動に移すことが最も重要とのことです。
60代で終活セミナーに参加した方は「セミナーをきっかけに、まず遺言書の作成と実家の片付けに着手しました。行動に移すと不思議と気持ちが前向きになり、『終活』が『今をより良く生きるための活動』だと実感しています」と語ります。
まとめ:60代からの終活は「計画」から「実践」へのシフト

60代の終活は50代とは明確に異なる特徴があります。50代が「将来への準備」に重点を置くのに対し、60代は「現実的な実践」が中心となります。時間的制約や身体的変化を意識しながらも、退職後の豊かな時間を活かして、より具体的かつ実践的な終活を進めていくことが大切です。
本記事で紹介した60代の終活の5つの特徴:
- 時間的制約を意識した優先順位づけ
- 退職後の時間の有効活用
- 実体験に基づく医療・介護の現実的選択
- 財産の「形成」から「分配と保全」へのシフト
- 人間関係と住まいの現実的な再構築
これらの特徴を踏まえた5つの具体的アクションを実践することで、より充実した終活が可能になります。
終活アドバイザーの言葉を借りれば、「60代の終活は、『やるべきこと』から『やりたいこと』へと視点を変える好機でもあります。人生の集大成として、自分らしい終活を実践していくことが、残された時間をより豊かに過ごすことにつながります」
60代からの終活は、決して「終わり」に向けた準備ではありません。むしろ、より自分らしく、より充実した「今」を生きるための実践なのです。